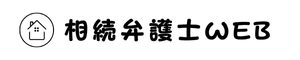遺留分とは?|相続で最低限守られる取り分のしくみと対策を弁護士が解説
遺留分とは、相続人のうち一定の人が最低限受け取れる法的な「取り分」です。たとえ遺言書があっても、遺留分を侵害された場合には「遺留分侵害額請求」ができます。本記事では、遺留分の基本から、侵害されたときの対応、トラブルを防ぐための生前対策まで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
遺留分とは?その法律的な位置づけ
遺留分とは、相続財産の中から一定の相続人に最低限保証される割合のことを指します。遺言や生前贈与で相続財産が他の人に多く与えられていたとしても、法律上、一定の相続人にはその取り分が保証されています。
遺留分の制度は、民法1042条以下に定められており、主に「配偶者」「子」「直系尊属(父母など)」に認められます。兄弟姉妹には遺留分は認められていない点は注意が必要です。
例えば、全財産を長男に相続させる旨の遺言があったとしても、次男や妻には遺留分の請求権が認められます。これにより、極端な偏りを防ぎ、遺族間の公平を保つ仕組みとなっています。
遺留分の割合と計算方法
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。以下が代表的なケースです:
- 配偶者と子 → 相続財産の1/2(遺留分割合:各人1/4ずつ)
- 配偶者のみ → 相続財産の1/2(全額が配偶者の遺留分)
- 子のみ → 相続財産の1/2(子ども全体で1/2)
- 直系尊属のみ → 相続財産の1/3(父母などで等分)
計算では、相続時の財産に加えて、1年以内の生前贈与や、特別受益(特定の相続人だけが大きな贈与を受けた場合)も加味されることがあります。
例:総財産6000万円、子ども2人のみ。うち1人に生前贈与で2000万円与えられていた場合は、実質8000万円がベースになり、遺留分全体は4000万円。もう1人の子はそのうちの2000万円(1/2)を請求できる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは?実務上の流れ
遺留分が侵害されていた場合、相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使できます(民法1046条)。これは以前の「遺留分減殺請求」に代わる制度で、現金での支払い請求が中心です。
手続きの流れは次のとおりです:
- 弁護士に相談し、遺留分の計算を行う
- 侵害額があると判断したら、相手方(受遺者や受贈者)に内容証明郵便で請求
- 任意に支払いがなければ、裁判所に訴訟提起
注意点として、遺留分侵害額請求には時効(1年)があります。「相続の開始と、遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内」に行使しなければなりません。
よくあるトラブルと生前対策
遺留分をめぐる相続トラブルは、次のようなケースで多く発生します:
- 遺言書で特定の子や第三者に全財産を与えていた
- 生前に偏った贈与があった
- 相続人同士の不仲・断絶
これを防ぐには、遺言書作成時に遺留分を侵害しないよう設計する、または「付言事項」で遺族に配慮した言葉を添えるのが有効です。
また、近年注目されているのが「遺留分放棄の事前手続き」です。これは家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄させる制度で、事業承継などで有効に使われます。
まとめ:遺留分対策は、弁護士への相談が最も安心です
遺留分の知識は、相続人にも、遺言を残す人にも重要です。
遺言で誰かに多く渡したい人は「遺留分の侵害にならないか」を知る必要がありますし、相続人側は「自分の取り分が侵害されていないか」に敏感になるべきです。
相続問題は、感情や人間関係が絡むため、法的知識だけでは対処しきれないこともあります。
相続トラブルを避けるためにも、早めに弁護士にご相談ください。
当事務所では、相続に強い弁護士が、遺言・遺留分・遺産分割までワンストップで対応いたします。
初回無料相談も受付中。お気軽にご連絡ください。