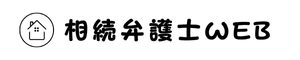事業承継の種類と進め方|親族内・第三者・M&A
中小企業の経営者が高齢化する中、事業承継は多くの経営者にとって避けて通れない課題となっています。特に親族への承継に限らず、信頼できる従業員や外部の第三者、さらにはM&A(企業の売買)など、承継方法は多様化しています。本記事では、事業承継の種類ごとの特徴や注意点、そしてスムーズに承継を進めるためのステップについて、法律実務の観点から丁寧に解説します。ご自身の状況に合った最適な承継方法を考える第一歩として、ぜひお読みください。
親族内承継|家族に継がせる伝統的手法
親族内承継のメリットとデメリット
親族内承継とは、経営者の子どもや親族に会社を引き継ぐ方法で、日本における中小企業の事業承継で最も一般的な手法です。最大のメリットは、経営理念や社風を維持しやすい点にあります。経営者と親族との間に信頼関係が築かれていれば、社内外の理解や協力も得やすく、スムーズな引き継ぎが可能になります。
しかし、デメリットも存在します。まず、後継者となる親族に経営能力があるとは限らず、従業員や取引先の不安材料となることがあります。また、複数の子どもがいる場合、誰が後継者になるかで争いが起こる可能性もあります。特に相続とセットで考える必要があるため、遺留分(いりゅうぶん:法定相続人に保障された最低限の相続分)など相続人間の調整が重要です。
さらに、株式や不動産などの資産を特定の親族に集中させる必要がある場合、他の相続人との間で公平性の問題が生じることもあります。こうしたトラブルを防ぐためには、早期に事業承継計画を立て、民法や会社法に基づく適切な手続きを進めることが求められます。
後継者の選定と育成のポイント
親族内承継を成功させるには、まず「誰に継がせるか」を明確にすることが出発点です。後継者として適任であるかどうかは、単に血縁関係だけでなく、経営に対する意欲・能力・社内外からの信頼といった多面的な観点から判断する必要があります。
選定後は、計画的な育成が不可欠です。たとえば、一定期間、他社で勤務させて経営の基礎を学ばせる「外部修業」や、段階的に社内で役職を上げながら現場感覚とマネジメントを学ぶ方法などがあります。また、税務・法務・財務などの基礎知識を身につけさせ、専門家と連携できる体制を整えておくことも重要です。
後継者育成には時間がかかるため、最低でも5年〜10年程度の準備期間を見込んでおくのが望ましいとされています。経営者が元気なうちから「事業承継計画書」の作成や、定期的な後継者との経営会議などを通じて、段階的にバトンタッチする体制を整えていきましょう。
相続と事業承継税制の活用
親族内承継では、経営権の移転と同時に、自社株式などの財産の相続が伴います。特に、会社の株式が相続財産に含まれる場合、その評価額によっては多額の相続税が発生し、承継の障害となることがあります。こうした場合に活用できるのが「事業承継税制」です。
事業承継税制とは、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代経営者から自社株式を贈与または相続により取得した場合に、その株式にかかる贈与税・相続税の納税を猶予、または免除する制度です(租税特別措置法第70条の7の2など)。この制度を活用することで、株式の評価額が高くても、現金納付の負担を大幅に軽減できます。
ただし、制度を利用するには、都道府県への「特例承継計画」の提出や、承継後の5年間にわたる継続雇用など、細かな要件を満たす必要があります。制度改正も頻繁に行われているため、適用を検討する際には、税理士や弁護士など専門家のアドバイスを受けながら、慎重に準備を進めることが重要です。
従業員・役員への承継|信頼ある社内人材へのバトンタッチ
従業員承継の特徴とメリット
従業員や役員への承継は、親族に後継者がいない場合や、親族内承継が困難な場合の有力な選択肢です。社内で長年働いてきた従業員や役員であれば、会社の事業内容や経営方針を深く理解しており、従業員や取引先からの信頼も厚いケースが多いため、スムーズな承継が期待できます。
また、現経営者がリーダーとしての資質を見極めやすく、承継後の経営方針についても共通認識を持ちやすい点がメリットです。特に、組織文化の継続や社員のモチベーション維持という観点からは、社内の人材に承継することの価値は非常に高いといえます。
一方で、承継に必要な資金面の課題があります。自社株式を買い取る資金を用意できない場合も多いため、持株会の活用や、信託、種類株式の設計などを通じた工夫が必要です。また、法的には「経営権の委譲」と「株式の移転」は別の手続きになるため、どちらも確実に行う必要があります。これらを適切に行うためにも、専門家の関与が重要です。
株式取得と資金調達の課題
従業員承継では、後継者が自社株式を取得することが大きなハードルとなります。中小企業の株式は非上場で市場性がなく、かつ評価額が高額になることが多いため、個人で買い取るのは困難なケースが少なくありません。これを解決する手段としては、以下のような方法があります。
まず、経営者からの分割払いや、株式の贈与・信託を活用して段階的に移転する方法です。また、中小企業投資育成株式会社などの公的支援機関や、金融機関の承継支援ファンドからの融資・投資を受けるケースもあります。これにより、経営に必要な資金調達の道が開かれます。
加えて、経営者が保有する株式に議決権制限を設けた「種類株式」を活用し、段階的に経営権と所有権を分離・移譲することで、実質的な承継を進めることも可能です。いずれの方法も、会社法や税法に基づく慎重な設計が求められるため、司法書士や税理士、弁護士などと連携した総合的な支援体制が欠かせません。
従業員承継を成功させるための準備
従業員承継を成功に導くためには、早期からの準備と、会社全体での合意形成が重要です。まず、候補者の選定段階で、単に勤続年数が長いという理由だけでなく、リーダーシップやマネジメント能力、会社の将来を担うビジョンを持っているかどうかを慎重に見極めることが必要です。
選定後は、現経営者からの業務引継ぎを段階的に行いながら、財務・人事・取引関係など経営全般を実務で経験させることが有効です。また、社内外への周知や信頼獲得も大切で、現経営者が公に「次期社長」として紹介し、役員会や従業員との交流を深める機会を意図的に設けることが推奨されます。
さらに、会社の定款や株主構成、就業規則などについても見直しが必要です。後継者に権限が集中しすぎないようにガバナンス体制を整備したり、支配権の過渡期におけるトラブルを防止する仕組みづくりが不可欠です。こうした準備を通じて、従業員承継は会社全体を巻き込んだ前向きな改革の契機ともなり得ます。
第三者承継・M&A|外部の力を活用した承継戦略
第三者承継とは?M&Aとの違い
第三者承継とは、親族や社内の従業員以外の外部の人物や企業に事業を引き継ぐ方法です。特に企業買収・合併を含むM&A(エムアンドエー:Mergers and Acquisitions)は、第三者承継の代表的な手段として広く活用されています。M&Aは、買い手企業が売り手企業の株式や事業を取得し、経営を引き継ぐことで事業を継続させる仕組みです。
第三者承継の大きな特徴は、「適任者が社内や親族にいない場合でも選択肢を確保できる」点にあります。特に後継者難が深刻な中小企業にとっては、事業の存続と従業員の雇用を守るための現実的な手段となっています。また、買い手側にとっては、新規事業への参入や事業拡大の機会ともなります。
一方、M&Aには法務・財務・税務などの詳細なデューデリジェンス(事前調査)が必要で、買い手との交渉や条件整備に時間とコストがかかります。事業の売却価格や契約条件によっては、創業者利益(いわゆる“出口戦略”)の獲得も可能ですが、買い手の企業文化との整合や従業員の不安への対応など、慎重な配慮が求められます。
第三者承継・M&Aの進め方と実務の流れ
第三者承継やM&Aを進める際には、段階的な準備と専門家のサポートが成功の鍵となります。一般的な流れは、①承継方針の決定、②企業価値の算定、③買い手候補の選定、④条件交渉、⑤基本合意書・最終契約書の締結、⑥引き継ぎ・クロージング、という手順で進みます。
まず最初に行うべきは「自社の現状分析と価値評価」です。中小企業のM&Aでは、売上や利益だけでなく、顧客基盤、技術、ブランド、従業員の技能などの無形資産も評価対象となります。このため、会計士や中小企業診断士と連携して「企業価値の見える化」を行うことが重要です。
その後、買い手候補の探索には、M&A仲介会社や士業専門家のネットワークを活用します。候補が決まれば秘密保持契約(NDA)を結び、詳細な資料を提供し、デューデリジェンスに入ります。交渉を経て条件がまとまれば、基本合意書、最終契約書へと進みます。契約後もスムーズな引き継ぎを行うために、一定期間、旧経営者が残る「引継ぎ支援型」の体制が取られることも多くあります。
成功のポイントと注意点
第三者承継やM&Aを成功させるためには、経営者自身の「目的意識」と「柔軟性」が重要です。単なる高値売却ではなく、「従業員の雇用維持」や「顧客への影響最小化」など、自社が守るべき価値を明確にし、それを実現できる相手を選ぶ視点が不可欠です。
また、M&Aは買い手と売り手双方の信頼関係が前提となるため、情報開示の正確性とタイミングが成功に直結します。財務データの整備、契約書類の一元管理、知的財産権や許認可関係の整理など、事前の「経営の棚卸し」が求められます。中小企業では特に、経営者の個人保証や会社と家族の資産の混同などがリスク要因となるため、早い段階から専門家の助言を受け、課題をクリアにしておくことが大切です。
さらに、M&Aによる承継は従業員や取引先にとって大きな変化となるため、情報発信と心理的ケアが欠かせません。社内には十分な説明と納得を促し、外部には信頼関係を損なわないよう段階的な発表を行うなど、コミュニケーション戦略も成功のカギとなります。法務・税務・労務の観点からも細心の注意を払い、専門家チームによる包括的なサポート体制を整えることが不可欠です。
事業承継の進め方|計画から実行までの流れ
事業承継計画の立案と基本ステップ
事業承継を円滑に進めるためには、「計画的な準備」が何よりも重要です。中小企業庁が示す「事業承継ガイドライン」でも、早期の着手と計画立案の重要性が繰り返し強調されています。一般的には、以下の5つのステップで進行するのが理想とされます。
①現状分析(経営者・会社・家族の状況整理)、②後継者の選定・育成、③承継方法の決定(親族内、従業員、第三者など)、④承継計画の策定、⑤実行・モニタリング、という流れです。
特に重要なのが「後継者の選定と育成」と「承継方法の決定」です。これらは経営者の意思だけでなく、家族構成や会社の経営状況、従業員の士気、株主構成などさまざまな要因を総合的に考慮して判断する必要があります。そのうえで、承継スケジュールを年単位で設定し、毎年の進捗を見直すことで、確実に実行に移すことができます。
承継が「一度にすべて移すもの」ではなく、「段階的なバトンタッチ」であるという意識が大切です。代表交代、株式譲渡、取締役会構成の変更、取引先・従業員への説明など、工程を分解し、無理のない計画で実行していきましょう。
関係者との調整と合意形成
事業承継は、経営者と後継者だけの問題ではなく、株主、従業員、取引先、金融機関、家族など、多くの関係者が関わるプロセスです。したがって、承継を円滑に進めるためには、関係者との丁寧なコミュニケーションと合意形成が欠かせません。
たとえば、株主が複数存在する場合は、後継者が過半数以上の議決権を持てるよう、株式の集約や種類株式の活用を検討する必要があります。また、会社と家族の財産が混同している場合には、整理・分離を行い、透明性のある財務状況を構築することが求められます。
従業員や取引先への説明も重要です。突然の代表交代は不安を招くため、後継者が徐々に表舞台に立ち、信用を築くプロセスを踏みましょう。さらに、金融機関との信頼関係を維持するためには、承継後の経営方針や財務体制について説明を尽くし、融資条件や保証内容を見直すことも検討するべきです。
こうした合意形成は、一朝一夕には実現できません。だからこそ、早期からの対話と準備が、事業承継成功の最も重要な要素となるのです。
承継に伴う法的・手続的対応
事業承継には、様々な法的・手続的な対応が必要です。まず代表者交代に伴って、法務局での登記変更手続が必要になります。これは、会社の代表取締役が変更されたことを正式に登記簿に反映させるもので、会社法(第915条)に基づき、変更後2週間以内に申請する必要があります。
また、後継者への株式の譲渡や贈与に伴っては、契約書の作成や株主名簿の書き換え、譲渡制限株式の場合には取締役会の承認手続なども必要となります。これらを怠ると、株主権の行使に支障が出たり、承継が無効とされるリスクもあります。
税務面でも、贈与税・相続税・譲渡所得税などが関係してきます。特に株式の評価額が高額な場合には、先述した事業承継税制の活用が不可欠です。制度の適用には、都道府県への「特例承継計画」の提出や5年間の継続雇用の確保など厳格な要件があるため、税理士と連携しながら進めましょう。
さらに、就業規則や定款の見直しも推奨されます。新しい経営体制に合わせて、取締役会の構成や業務分掌、報酬体系などを再構築することが、スムーズな経営移行と社内の納得感につながります。法務・税務の専門家を交えた総合的な支援体制のもと、確実な手続きを実施することが大切です。
円滑な承継に必要な法務と税務の基礎知識
株式承継における法的注意点
事業承継において、会社の「支配権」を引き継ぐ手段として最も重要なのが、株式の承継です。特に非上場会社の場合、株式は家族や特定の株主に集中していることが多く、その移転方法には細心の注意が必要です。承継方法としては、生前贈与、譲渡、遺言による相続などがあり、それぞれ法的・税務的な影響が異なります。
例えば、自社株が「譲渡制限株式」に該当する場合(会社法第107条第1項)、株式を第三者に譲渡するには取締役会等の承認が必要です。これを怠ると、譲渡が無効とされるおそれがあります。また、株主間契約や会社の定款に「買戻し条項」や「譲渡禁止条項」などが含まれている場合もあり、承継時には事前確認が必須です。
さらに、後継者が少数株主であっても実質的に会社を支配できるようにするため、種類株式の発行(会社法第108条)などを活用して議決権に差をつける方法もあります。これにより、相続人間の分散所有による経営混乱を避けることができます。
株式承継の失敗は、経営権の空白や相続トラブルを引き起こす原因にもなります。したがって、株式の保有状況・承継方法・契約内容を事前に整理し、法的整合性を確認した上で進めることが極めて重要です。
税務上の評価と事業承継税制のポイント
事業承継においては、株式や不動産などの資産を「いくらの価値で引き継ぐか」が税務面での大きな課題となります。特に非上場株式の評価は、原則として「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」など、国税庁が定める評価方法に従って行われます。これらの評価額が高額になると、贈与税や相続税が多額になるおそれがあります。
こうした負担を軽減するために設けられているのが「事業承継税制」です。この制度は、後継者が一定の条件を満たせば、株式の贈与税・相続税の納税を猶予または免除する仕組みで、中小企業の円滑な承継を後押しする政策的制度です(租税特別措置法第70条の7の2等)。
適用を受けるためには、「特例承継計画」の提出(2027年3月31日まで)、「認定経営承継会社」の要件の充足、5年間の継続雇用の確保、株式の継続保有・経営継続などが求められます。制度を活用することで、たとえば1億円超の株式評価額でも、実質的に納税なしで承継が可能になるケースもあります。
ただし、制度は一度適用を受けた後も「継続要件」があり、条件を満たさなくなると猶予された税金を一括で納税しなければならなくなるリスクもあります。そのため、活用にあたっては必ず税理士などの専門家に相談し、制度の要件を十分に理解した上で計画的に承継を進める必要があります。
遺言・信託の活用と民法上の留意点
事業承継では、経営者が死亡した場合に備えて「遺言」や「民事信託」を活用することが、円滑な引き継ぎのために有効です。特に、自社株式を誰にどのように承継させるかについて、明確にしておくことが重要です。
遺言は、民法に定められた方式に従って作成することで、被相続人(亡くなった経営者)の意思を法的に実現する手段です。公正証書遺言であれば、信頼性が高く、家庭裁判所の検認も不要なため、トラブル回避に有効です。例えば「全株式を長男に相続させる」旨を明記しておくことで、相続開始時に経営権の空白を防ぐことができます。
一方、民事信託(家族信託)を活用すれば、生前のうちから信頼できる人物に経営権を移しておきつつ、利益の受け取りは自分が継続する、といった柔軟な設計が可能です。民法と信託法の枠組みを組み合わせて使える点が、相続では対応しきれない複雑な事情に対応する力となります。
ただし、遺言・信託いずれを用いる場合も、「遺留分(いりゅうぶん)」に注意が必要です。遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に認められた最低限の取り分であり、これを侵害すると「遺留分侵害額請求」の対象となり、承継計画に支障が出ることもあります。事前に法的リスクを把握し、遺留分対策を含めたトータルな設計を行うことが肝要です。